乾性油概要
油の分類
油彩技法で使用する油は、「精油」と「油脂」に大別される。「揮発油」と「不揮発油」と言っても良い。両者は、性質も役割も大きく異なる。揮発油は、空気中に蒸発して画面に残らない。テレピン、ペトロールなどがこれにあたる。「不揮発油」は、サラダ油のような油脂で、時間が経過しても空気中に揮発したりしない。画材では亜麻仁油(リンシードオイル)やポピーオイルがよく使用される。揮発油については、揮発油の頁で解説することとし、ここでは不揮発油(油脂)について解説する。
油脂は乾性油、不乾性油、半乾性油に分類される。亜麻仁油、ポピー油、クルミ油は薄く塗布すると乾燥(固化)し始める。このように、薄い膜にしたときに常温で乾燥する油を「乾性油 Drying oilと呼ぶ。逆に、オリーブオイルや落花生油など、いつまでも液体のままで乾くことがないオイルを「不乾性油」と呼ぶ。その他、乾燥しないわけではないが、非常に時間のかかるものや、いつまでもべたついて完全に乾燥しない油を「半乾性油」と呼ぶ(ゴマ油、ナタネ油など)。なお、塗布テストしたところ、数年待てるならば、半乾性油でもしっかりとした皮膜を形成して乾燥したが、実際の絵画制作では現実的ではない。
油絵具の材料として使用されるのは「乾性油」であり、代表的なものにリンシードオイル(亜麻仁油)、ポピーオイル(ケシ油)、ウォルナッツオイル(胡桃油)などが挙げられる。油絵具とはこの乾性油で顔料を練ったものである。油絵具がキャンバス上に置かれると、絵具のなかの乾性油は酸素を取り込んで固まり、顔料を定着させるとともに、油絵独特の透明感と光沢を与える。この点が、蒸発乾燥する媒材を使った他の絵具との大きな違いと言える。
乾燥の仕組み
次に油絵具(乾性油)が乾燥する仕組みと、その過程について考えてみる。水彩絵具の場合は、溶剤である水が蒸発して顔料と接着剤が残る状態になることが乾燥工程のメインと言える。それに対し、油絵具の場合は、絵具の中の乾性油が蒸発ではなく、固化することが乾燥工程の要である。前者を蒸発乾燥、後者を固化乾燥と言う。乾性油は、酸化と重合という過程を経て固化乾燥する。分子構造の中に酸素と結びつき易い構造を持っており、画面に塗られた乾性油は、酸素を取り込みはじめる。リンシードオイルのように酸素と結びつく構造が多い油は、乾燥が速くかつ丈夫な皮膜を形成する。ポピーオイルのように、そのような構造が少ない油は乾燥が遅く、形成する皮膜も弱い(このような酸素と結びつきやすい構造がほとんどないオイルはいつまで経っても乾燥しないので不乾性油となる)。酸化の次には、ゆっくりと分子同士が結びつく重合の行程が始まる。酸素を仲立ちとして分子同士が結合、高分子となり、そして油彩画は丈夫な皮膜を形成する。
画面に塗られた油絵具の層は、酸素に直接触れる表面の皮膜から乾燥が始まり、しだいに内部が乾燥してゆく。あまり厚く絵具を塗ると表面と内部の乾燥の時差により、皺よりや亀裂が起こる。下の層が乾いてないうちに上に塗り重ねれば、ますますその危険は大きくなる。特に、乾燥の遅い絵具や油の上に、乾燥の速い材料の層を置くと、大きな亀裂が走ることもある。制作途中や制作後間もなく亀裂が出来る場合は、制作の手順に問題があると言える。
画面上の油絵具は数日で指触乾燥(指で触れることができる程度の乾燥)までたどり着くが、しっかりと乾燥し、保護ワニスが塗れるぐらいになるのは、半年から1年を要する。さらに酸化重合の反応はその後も数十年のあいだ続くと言う。描いてからそれほど年月の経っていない皮膜は、柔軟性を持っており、キャンバスを巻いて移動するようなことができる(厚塗りの場合、マチエールが壊れるので巻くことは難しいが)。しかし、乾燥の行程が完全に終了する頃には、画面の皮膜は柔軟性を失って、湿度変化による支持体の伸縮にすらついてゆけず、細かなひび割れが走るようになる。古い油絵には大なり小なり細かいヒビが無数に見られるが、このようなヒビは油彩画なら当然発生するものである。
乾性油の乾燥速度は環境にも大きく左右される。気温の高い方が速く乾燥し、低いほうが遅くなる。夏に比べて、冬の方が、絵具の乾燥が遅い。リンシード油や乾燥剤の入ったメディウムを使用している分には、それほど顕著な差は感じないかもしれないが、特にポピー油やスタンド油を使うと、はっきりと乾燥の遅さを感じることだろう。その他、暗所より光の当たるところの方が乾燥は速い。暗所では特にリンシード油が暗変する性質があるので、制作中や制作後に暗所に置いて乾燥を待つのは避けるべきである。ただし、直射日光に当てるのは良くないという話である。また、個人的な経験では、空気の流れのある方が乾燥が速いような気がする。塵を避けるため、制作途中からガラス入りの額縁に入れていたことがあったが、光はあたっているし、真空状態というわけでもないのに、やはり乾燥は遅くなる。
油脂用語
油脂の主成分である脂肪酸の分子は、数個から十数個の炭素原子が一列につながって出来ている(画材用途の油のほとんどは18個)。炭素原子は4つの原子とつながることができる。わかりやすくイメージするために、4つの腕を持っていると考えてみよう。4つのうち2つは、左右の炭素原子と結びつくために使われている。右の炭素と結びつくのに1本、左の炭素と結びつくのに1本。○-○-○-○-○こんな感じである。そして残り2本の腕は、水素原子を掴んでいる。4つ腕全部使っているので安定しており、これを飽和の状態という。
しかし、たまに隣の炭素と結びつくのに、2本の腕を伸ばしている炭素原子がいたりする。普通は○-○-○-○-○という感じでつながっているのが、○-○=○-○-○のように二本の触手でつながっている箇所がある。これを二重結合という。このように片側の炭素と2本の腕で繋がっている場合、そのうち1本の腕を離して、酸素を掴むことができる。というより、むしろ積極的に酸素を掴もうとする。このような二重結合を持つ脂肪酸を不飽和脂肪酸と呼ぶ。
オレイン酸、リノール酸、リノレン酸が不飽和脂肪酸に該当する。このうちオレイン酸は1つの分子に二重結合が1コあるだけなので、乾燥性はほとんどない(多くの植物油はこのオレイン酸が主成分)。これに対してリノール酸は1つの分子に二重結合が2コあり、それなりの乾燥性を持っている。ポピー油、サフラワー油などは、このリノール酸が主成分である。リノレン酸は二重結合を3コ持っている。そのため乾燥性が強く、特にリノレン酸を多く含む亜麻仁油(リンシードオイル)は、乾性油の代表格と言える。
- オレイン酸 … 二重結合が1コだけ。乾燥性はほとんどない。
- リノール酸 … 二重結合が2コ。ポピーオイル、紅花油の主成分。
- リノレン酸 … 二重結合が3コ。強い乾燥性。亜麻仁油の主成分
下表は各オイルのリノレン酸、リノール酸の含有量(数値はかなり大雑把に整理している)。
| リノレン酸 | リノール酸 | その他の脂肪酸 | |
|---|---|---|---|
| リンシードオイル | 6 | 1~2 | 3 |
| ポピーオイル | 0 | 7 | 3 |
| ウォルナッツ | 1 | 6 | 3 |
ヨウ素価とは、二重結合部分(不飽和部分)にヨウ素を付加させ、ヨウ素が付加できる分量を量った値。ヨウ素価によって、二重結合の量が分かり、乾燥度を計る目安となる。あるいは逆にヨウ素価から油脂名を推測することも可能。『絵画材料事典』にあったヨウ素価を以下に抜粋。
- ポピーオイル … 140-158
- ウォルナッツ … 140-150
- リンシード … 170-195
参考文献:原田一郎著『改訂増補・油脂化学の知識』
乾性油の精製・加工
リンシード油、ポピー油など、油絵で使用する乾性油は植物の種子から採られるものであるが、搾油されたばかりの油は濃い褐色をしており、多くの不純物を含んでいる。不純物を取り除き、漂白したものが、市販の画材用オイルの数々である。リンシードオイル、ポピーオイルなど、無冠の名称のオイルも、精製工程を経ている。あるいはブリーチド(漂白)オイル、リファインド(精製)オイルという名称の場合もある。この時点のオイルを、「生のオイル」と呼ぶ。オイルの精製、漂白については、乾性油の精製ページで詳しく紹介している。
「生のオイル」を日に晒したり、加熱するなどして加工したものを加工油と呼ぶ。例えば、亜麻仁油を空気と日に長期間晒して変性させたサンシックンド・リンシードオイルは、生のオイルよりも耐久性、乾燥性に優れ、そのうえ黄変しにくいなど、優れた性能を獲得する。その他、ボイルしたり、鉛を加えたりなどの様々な加工法がある。昔の画家は生の乾性油をそのまま使用するのではなく、熱を加えたり、空気に晒したりして性質を変えてから使うことがむしろ多かったという。サンシックンドなど、オイルの加工方法については、乾性油の加工ページで紹介している。
生の乾性油
リンシードオイル

別称:亜麻仁油(あまにゆ)、英語表記:Linceed Oil
油彩技法では最も重要な油であり、白などの黄変の影響が出やすい箇所以外は、リンシード油、またはリンシード油を加工したオイルを使用するのが望ましい。乾燥が速く、丈夫な皮膜を作るが、黄変する傾向がある。亜麻の種子から搾り出されたリンシードオイルは、右の画像のような、透明な黄褐色をしている。これを太陽の下で晒す、水で洗う、白土等色素を吸着させるなどして無色透明に近づける。手作業で精製したオイルは、室内の暗い場所に置いておくと、若干だが再び褐色に戻ってくるが、日光の当たる場所に置けばまた透明になる。市販品は強力に精製されているので、暗所に置いても極端な変化は見られない。ただし、市販品と言っても、画材店でオイルの棚を見ればわかる通り、ほとんど無色のものから、黄金色をしたものまで様々であり、そろらくメーカーによって精製方法やその程度の違いがあると思われる(画材店の保管の違いで暗変している可能性もある)。
亜麻仁油で描かれた絵を暗所に置くと、画面が暗くなってくることがある。暗くなった絵は、光に当てると明るさが戻ってくる。油性地のキャンバスが黄色くなっていたとしても、これはリンシード油が使用されているためであり、不良品というわけではない。むしろリンシード油を使用している証拠と言える。
多くの市販絵具では顔料を練る媒質として、黄変の心配がある白や淡色にはケシ油またはサフラワーオイルを使用し、黄変の心配のない色に亜麻仁油を使用していることが多い。全色をケシ油で練っているシリーズもある。下地塗り用のホワイトは堅牢性を求められるので、リンシードが使われている。描画時には、リンシード油の黄変を避けるための工夫として、ポピー油とリンシード油を混ぜて使うのも良いのかもしれない。
ポピーオイル

別称:芥子油、ケシ油。英語表記:Poppy oil、またはPoppy-seed Oil
ケシの種子から採れる油。黄変が少ないので、白や青、明るい部分の描写に適している。堅牢性では亜麻仁油に劣り、乾燥は遅い。ポピーオイルの使用に関しては17世紀の手記にもたびたび登場するが、当時の主役はリンシード油とクルミ油であり、ポピーオイルが広く使われるようになったのは、ずっと後のことである。今日ではリンシードオイルと並んで最も一般的なオイルとなっている。市販のチューブ絵具では、白や淡色を練るのにポピーオイルが使われている。印象派以降の画風のせいか、黄変が特に嫌われる傾向があり、リンシードよりポピーの方が好まれているようだ。なお、チューブ絵具に使用される油としては、最近はポピー油と良く似た性質のサフラワーオイルの方をよく目にする。
リノール酸が主で、リノレン酸を全く含まないため、乾燥するのに時間がかかる。乾燥した後も皮膜が柔らかく、亀裂が生じやすい。乾燥が遅いのでポピーオイルで描いた上に重ね描きするときは、ある程度画面がしっかり固まっているか確認した方が良い。しかし下層のポピー油が完全に乾燥していたとしても、その上に亜麻仁油などの硬く固まる材料を使って描くと、亀裂の原因になる。下塗り、地塗り等にはリンシードオイルを使うのが良い。
リンシード油に比較すると黄変は少ないが、全く黄変しないわけではない。以前、明色の顔料を練ろうとして、大理石の上にポピーオイルを敷き、数週間放置してしまったことがあったが、気が付くとすっかり黄色くなっていた。他の研究所等で行なった黄変試験などを見ても、明らかに黄変している。
ポピーオイルの原料は、ケシの種子だが、ケシはアヘンが採れるために、基本栽培ができない。私は東京薬用植物園で見ただけである。そのような植物ということもあってかしらぬが、ポピーオイルの仕入れは高コストのようである。国内の画材メーカーは共同で出資して一括購入しているという話を聞いたことがある。ホワイト絵具では、ポピーオイルとサフラワーオイルを使用したもので価格に差がある。ちなみに種子には毒はないという。ケシ種子はあんパンの上に載っている。菓子作りように販売されているので、搾油機があれば自分で絞ることもできる。
ウォルナットオイル

別称:胡桃油、クルミ油、くるみ油、英語表記:Walnut Oil
胡桃の仁から採る油で乾性油の一つ。かつてはリンシード油と並んで、油彩技法のための重要な媒材だった。傾向としてはイタリアでは胡桃油が、北方ではリンシード油が好まれたようである。リンシードオイルより黄変が少なく、白や青、明るい部分に使用された。リノール酸が約6割、リノレン酸を1割強含む。リノール酸の方はポピーオイルに多く含まれている脂肪酸で、乾燥が遅く皮膜は弱いが、黄変し難い性質を持つ。リノレン酸はリンシードオイルに6割も含まれている脂肪酸で、乾燥が速く丈夫な皮膜を作るが強く黄変する。ウォルナットオイルは、リノール酸が主成分だが、リノレン酸も1割強ほど含み、少し強度の増したポピーオイルに近いと考えることができる。
| リノリン酸 | リノール酸 | その他の脂肪酸 | |
|---|---|---|---|
| リンシードオイル | 6 | 1~2 | 3 |
| ポピーオイル | 0 | 7 | 3 |
| ウォルナット | 1 | 6 | 3 |
現在、クルミ油を画材店で見かけることはほとんどない。ホルベイン工業技術部(編)『絵具材料ハンドブック』には「クルミ油はわが国でも、太平洋戦争後の一時期に国産クルミから搾油精製して絵画用油として使用されたことがあるが、現在では原料入手が難しい点から使用されていない
」とある。『絵画材料事典』には「悪臭を放つようになり易かったり、この油で練った工場製のチューブづめの絵具は全く保存がきかないなどの欠点があることから見すてられるようになったといわれる
」とある。最近まで、国内で入手できる胡桃油は、(画材用では)ルフラン(仏)のブラックオイルのみだった。これは鉛を入れて加熱したブラックオイルなるもの加工されている。数年前からマイメリ(伊)の画材が輸入され、生の胡桃油が買えるようになった。また、画材店に拘らず、広く塗料用品店を覗けば、胡桃油を扱っている店は多くある。Laurie,The Painter’s Methods and MaterialsのWulnat Oilの解説によると、サンシックンドにすると乾燥も亜麻仁油並に速くなり、色も透明になるという。ルフラン社の製品も加工油であるし、加工して使用するのが使用方法としては正しいのかもしれない。個人的には、生の胡桃油に樹脂を加えつつボイルしたものを、黄変して欲しくない箇所に限って使用している(まだまだ使用年数が足りないので、材料に対する評価はできないが)。
サフラワーオイル

別称:紅花油、英語表記:Safflower Oil
リノール酸が主成分の乾性油で、性質はポピーオイルと似ている。黄変は少ないが、乾燥が遅く、耐久性も亜麻仁油に劣る。市販の油絵具では、白などの明色を練るのによく使われる。以前はポピーオイルが使われていたものだが、最近急速にサフラワーオイルに代わりつつある。特に欧米の絵具は圧倒的にサフラワーオイルが主流となっている(食料用に大量生産されているサフラワーオイルの方が安定して調達できるのかもしれない)。しかし、ポピーの代替だとしても、サフラワーがポピーに劣るという話は聞いたことがない。油脂の本に掲載されている脂肪酸の表によれば、ポピーよりも若干リノール酸の数値が大きく、またほんの僅かながらリノレン酸も含まれているため、もしかしたらポピーより堅牢かもしれない。
市販の白絵具を練るのに使われているのだから、現代の油絵具の影の主役とも言えるが、サフラワーオイルのみが単体で画材用として一般に販売されているのを見たことはない(少なくとも日本の画材メーカーの商品一覧には無い)。食用の紅花油はどこでも買えるが、酸化防止剤が入ってる可能性もあり、これを画材として使うのは躊躇われる。また、食用の紅花油はハイオレイック種と言って、品種改良によりリノール酸をオレイン酸に置き換えたものが登場している。オレイン酸はほとんど乾燥性はないので、試したわけではないが、乾燥しないかもしれない。昔は、サラダ油(混合油だが紅花油が含まれていることが多い)と顔料を混ぜると油絵具になってしまったものだが、最近はそうもいかなくなりつつある。
サンフラワーオイル
向日葵油、ヒマワリ油、英名:Sunflower Oil。
向日葵の種から採るオイルで、ロシア絵画に広く使用された。ひまわりは食用から燃料まで用途の多い花である。原産地は北アメリカで、1500年前後に西ヨーロッパに伝えられた。初めは観賞用として栽培されたが、やがて食用や飼料、搾油などの目的で大規模に栽培されるようになった。特にロシアで品種改良が進み、ロシアひまわりという巨大な花を持つ品種が作られた。リノール酸を多く含み、性質はポピーオイルに似ている。日本の画材店ではまず置いていないが、食用のひまわり油ならスーパーにいくらでもある。「酸化防止剤無添加」「一番搾り」と表示されているものなら使用できる可能性がある。私は以前俵屋工房から購入したが、実はまだ使用したことがない。同工房の試験では非常によい結果を出したそうである。
脱水ひまし油
英語表記:Castor oil。ヒマの種子(トウゴマ)から採取される油。種には毒素があるという。ひまし油は不乾性油だが、脱水素工程を経て変性させた「脱水ひまし油」は乾燥が早く黄変も少ないという。私自身は使用したことがない。
荏の油(えのあぶら)
別称:荏油、荏ノ油、荏之油、英語表記:Perrila Oil
「荏」の種子である「荏胡麻」から取れる油で、古くから日本の職人の間で使われてきた。「江戸時代の洋風画に使用された油は荏の油が主流であった
」(歌田眞介『油絵を解剖する』P.96)。リノリン酸の割合が50%程度で、リンシードオイルに近いと言える。亜麻仁油より速く乾燥するが、強い黄変が起こるという。油絵用の材料として売られていることはまずないが、ペンキや工芸材料の売り場にゆくと置いてある。サンプルとして入手しているが、画材用のリンシードオイルが幾種類も手に入る現状では、なかなか使用する機会が訪れない。
3.加工した乾性油
サンシックンドオイル

別称:日晒し油、日干し油、英語表記:Sun-Thickened Oil
乾性油を長期間太陽光に当てて酸化重合を進め、粘度を高めたもの。乾燥が速く、堅牢で透明感や光沢のある画面を作る。リンシード油を使用したものをサンシックンド・リンシードオイル、ポピー油を使用したものをサンシックンド・ポピーオイルなどと呼ぶ。比較的水分になじみ易いので、テンペラ・グラッサ技法の際に、油成分として使用することもある。
サンシックンド・オイルは自分で作ることもできる。ガラス器など透明な容器に水を張り、そこに生のリンシードオイルを容れ、太陽に晒す。油の厚さは2センチぐらいが良いかと思う。上にガラス板を置いて埃が入らないようにする。空気が通るようにガラス板は少し浮かせておく。定期的にかき混ぜながら、数ヶ月間、太陽に晒す。こうして自製したサンシックンド・オイルは、ほぼ完全に近い透明色になる。市販のサンシックンド・オイル(写真右)が褐色なのは、水分を完全に除くために加熱するからである。この作業を行なわないと、商品をストックしているうちにビンが破裂する危険があるという。画材メーカーによって、ボイルする強さが違うようで、色の濃いものと薄いものがある。さらに、同じ画材メーカーの商品でも時期によって、色の濃さかなり大きく異なることがある。特に強く焼き色がついたものは、サンシックンド油ではなくボイルド油ではないか、という人もいる。自身でサンシックンドの加工を行なった場合、商品ストック時の危険さえ気にしなければ、透明なままのサンシックンドオイルを使うことができる。
スタンドオイル

英語表記:Stand oil、別称:重合油(Polymerized oil)
空気を遮断した状態で高温で過熱し、重合させたオイル。加熱する温度は250~300度Cで、加熱時間よって粘度が変わる。サンシックンドオイルのように酸素は吸収していない。酸素の仲立ちをせずに、熱によって炭素分子が同士が結びつき、極めて堅牢な画面を作るオイルとなる。加熱する時間が長くなると粘度が増し、市販のスタンドオイルのように粘っこくなる。ヨウ素価は減ってゆき、乾燥は生の油よりも遅くなる。しかし乾燥後の皮膜はずっと耐久性があり、黄変も起こり難くい。
スタンドオイルの名称の由来は、絵画材料ハンドブックには「オランダ語のstandhoudenheit(耐久性のある)からきた言葉
」とありますが、英語のstandには「ある」とか「置かれる」という意味があり、絵画材料事典では、「そのままで放置しておく(stando)と粘質物質が凝固して乾性油から分離してくる事実からこの名前が出ている
」とある。
大方のスタンドオイルは粘度が高く、乾燥が遅いので、このオイルを単体で使用するのは困難である。どちらかというと、自作画用液の素材の一部として優れた効果を出すと言える。特にグレース技法のためのメディウムを作ったり、テンペラ用のメディウムを作る際に役立つ。ペンキ用のスタンドオイルには、粘度による等級があったと聞く。『絵画材料事典』には弱・中・強のスタンドオイルの粘度とヨウ素価が掲載されている。日本でも、ペンキ屋では粘度に等級別のスタンドオイルが販売されていると聞いたので、尋ねた廻ったが、結局見つからなかった。「弱」のスタンドオイルを利用してメディウムを作成したかったのだが。しかし、画材メーカーによって、粘度が違うことがあり、流動性の高いスタンドオイルを入手したこともある。※現在は低粘度のスタンドオイルも販売されている。
ボイルドオイル

英語表記:Boiled oil、別称:煮アマニ油
空気を吹き込みながら、あるいは空気に触れさせながら加熱したオイル。加熱するために少し焼き色が付く。しっかり加熱したものは褐色で、あまり強く加熱していないものはほとんど透明なまま。鉛やマンガンなどの乾燥剤を入れて過熱する場合もある。いくつかの画材メーカーから市販されているが、製品によって使用感が異なる。
ブラックオイル

別称:鉛入りオイル、英語表記:Black oil。
鉛を入れて熱したオイル。油に5~10%の鉛を加えて焼くと真っ黒いオイルができる。このオイルは驚くほど速く乾燥し、堅い皮膜を作る。数時間もしないうちに重ねて描くことができ、一日経つと上にのせた絵具を弾くほどである。ふつうは他の画用液と混ぜて調整すると良い。古い絵の技法を紹介する本を読んでいると、鉛を入れてオイルを焼くことは、昔はかなり一般的だったようである。鉛白を含む絵具の層は丈夫で乾燥も速いことからも、使い方さえ正しければ乾燥剤として油膜に良い影響を与える。市販されているものでは、ルフラン(仏)のブラックオイルが唯一の製品で、これはウォルナットオイルをベースにしたブラックオイルだった。クルミ油の乾燥の遅さをうまく補っている。しかし、最近は日本のメーカーも発売しているし、海外のショップでもよく見かける。「ブラックオイルの作り方」のページにて、自製方法を紹介している。


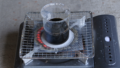
コメント